ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング』
川島隆太教授 篇
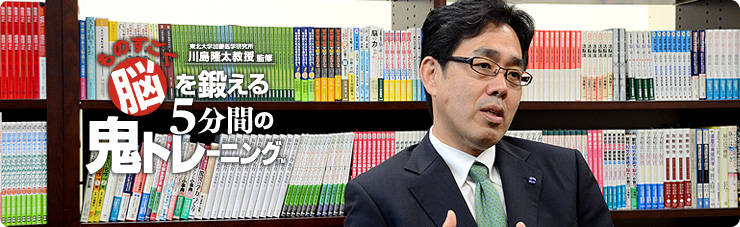
2. “脳の体積が増える”
- 岩田
- 一方で、2004年から2006年ぐらいの段階では、
「脳の中で何が起こっているのか?」という原理は、
はっきりと理論化されていませんでした。
そのために「科学として正しいのか?」というご指摘もあり、
ブームになってしまったがゆえに、
先生にご迷惑をおかけしたかもしれません。 - 川島
- いえいえ。
そうですね・・・『脳トレ』は、
「使っている人の脳に何が起こるのか?」という科学情報、
つまり“前頭前野が活性化する”という脳の働きを
タグとして商品につけた、はじめての試みだったんです。
それだけでもエポックメイキングでしたけど、
そこを解析してくれた方があまりいなかったことが、
少し残念ではありました。 - 岩田
- それから『脳トレ』を通じて、
「世代を超えて家族のコミュニケーションが起こった」
という価値もすごくあったと思うんですけれど、
そういう部分には必ずしも、陽が当たらなかったですね。
『脳トレ』で脳血流が増える、
すなわち脳が働いているということは
光トポグラフィー(※3)で実証されていますが、
その後、脳にどういう変化が起こるのかは、
あの時点では理論化されていませんでした。
その後、どのように研究が進んでいったのでしょうか?
光トポグラフィー=脳の活動状況を調べる医療機器。脳の表面、つまり運動野や言語野などの機能の活動測定を行う。
- 川島
- まず、高齢者の方々が『脳トレ』を遊ぶと、
さまざまな脳の働きがキチッと伸びることを
心理学のいろんな指標を使って証明しました。 - 岩田
- はい。
- 川島
- でも、DSの『脳トレ』ではない、
パソコン上で動く一部の記憶トレーニングソフトでは
脳の働きがキチッと伸びない、ということもわかったんです。
『脳トレ』ではないトレーニングは、
論理的には脳のトレーニングをしていても、
実際に光トポグラフィーで脳の計測をすると、
前頭前野に負荷がかかっていなかったんです。 - 岩田
- 『脳トレ』のトレーニングなので、
一見、似たようなことをしていても、
問題を読んで、計算をして、DSにペンで字を書くというように、
「いくつかの処理を同時に連携して動かしていかないと、
トレーニングになっていない」ということですよね。 - 川島
- はい。
「簡単にできるものだと脳に負荷がかからず、
トレーニング効果が出ないのでは?」
とわたしは仮説を立てています。
また、「脳に負荷がかかるかどうか」については、
脳計測をしてはじめてわかるものなので、
一見、論理的に正しそうなことをやっていても、
脳に負荷がかかっている証拠はないんです。

- 岩田
- つまり、光トポグラフィーなどで脳計測をして、
脳の血流がどれくらい盛んになったかで、
脳の負荷のかかり具合がわかるんですね。
実際に『脳トレ』をつくったときも、
先生から「こういう原理で」とお聞きして、
たくさんソフトをつくりましたが、
けっこうボツになりました。
「こうすれば脳が活性化するに違いない」と
論理的に思ってつくっても、
「逆にクールダウンしています」
ということもありましたから、
やっぱり測ってみないとわからないものなんですね。 - 川島
- はい。そこが心理学を学ぶだけではわからない、
脳の面白さでもあります。
「では、どうすれば脳の活動量を上げられるのか?」
というのは、『脳トレ』の開発でも大きなテーマでした。
『脳トレ』とは脳の働きの中でも、
記憶力の処理速度を速くするトレーニングなんですが、
その後の実験で、脳の体積を増やしたり、
いろんな認知機能を増やせることが証明できました。 - 岩田
- いま、先生がおっしゃった
“脳の体積が増える”というのは、
普通の方には想像しづらいと思うんですが、
それは、どういうことなのでしょうか? - 川島
- はい。わたしたちは脳の加齢現象を抑えるために、
高齢者の方々の脳がどう変化するかについて、
MRI(※4)という装置を使って測定していました。
たとえば大脳の皮質といわれる、
神経細胞層の厚みがどう変わるかも、計測できるんです。
MRI=Magnetic Resonance Imaging system。磁気共鳴画像装置。磁場と電波を用いて、体内などの画像を撮影する装置。
- 岩田
- それもやはり、加齢とともに衰えていくんですか?

- 川島
- はい、普通は減って、薄っぺらくなります。
皮質がいちばん分厚いのは8歳~10歳ころがピークで、
そこからはどんどん減ってしまうんです。
ただ、20歳ごろまでの減り方は整理統合とされ、
20歳から先は老化による短縮だと考えられているので、
自然なことだとされています。 - 岩田
- はい。
- 川島
- ところが2000年を過ぎたころ、
『サイエンス』(※5)という雑誌に、
「トレーニングでジャグリングをさせると、
ものの動きを感じる脳、つまり頭頂葉や側頭葉の体積が増える」
という論文が、突然、ポッと現れました。
これは「脳の変化が目に見えて起こった」
ということに対する、はじめての論文だったんです。 - 岩田
- はい。
『サイエンス』=1880年より、アメリカ科学振興協会から発行されている学術雑誌。
- 川島
- ジャグリングの例と同じように、
『脳トレ』をやると、脳の中でネットワークの変化が起こり、
脳の働きがよくなることが心理学的にわかっています。
『脳トレ』の場合は脳の処理速度のトレーニングでしたが、
今回の『鬼トレ』では“ワーキングメモリー”(※6)の容量を増やす、
つまり、「どれだけたくさんの記憶を一時的に頭の中に留められるか?」
というトレーニングにチャレンジしました。
“ワーキングメモリー”=作動記憶。情報を一時的に保ちながら操作・利用する記憶の過程をいう。ある目的を持って記憶した状況を、自分の中の複数の情報と照らし合わせて適切な対応をする脳の働き。
- 岩田
- “ワーキングメモリー”というのは、
一時的に覚えておいて、いつでも引き出せる状態。
たとえば電話番号を一瞬覚えて、
かけおわったらすぐ忘れる、みたいなのが、
ワーキングメモリーのひとつの存在、というか、
特色だと思えばいいですね。 - 川島
- はい。ワーキングメモリーの容量自体は、
いちばんトレーニングしづらい部分です。
じつは、メモリーの容量は老若男女問わず、
ある程度の量が決まっているんですが、
いわゆる“賢い人”はそれが多いわけです。
そこで大学生に1日に20分から1時間程度の
ワーキングメモリーのトレーニングを毎日つづけてもらったら、
特に前頭前野といわれる
高度な脳の働きをする部分の体積が、
左右の脳とも大きく増えているんです。
それとおどろくことに、
クリエイティビティーまで上がっていたんです。
