『ニンテンドー3DS』ソフトメーカークリエーター 篇
第11回:『BIOHAZARD REVELATIONS』
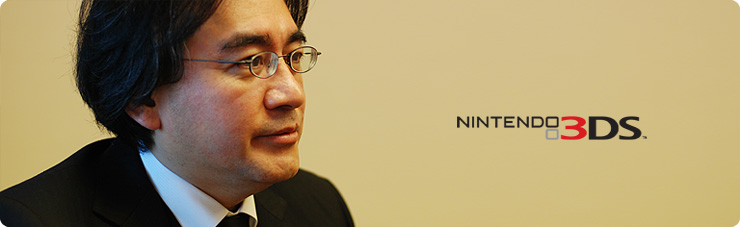
5. “怖さ”と“没入感”
- 岩田
- 今回、『バイオハザード』をつくるうえで
欠かせなかったポイントはどこになりますか? - 中西
- やっぱり、イベントなどでお客さんに
かなり触ってもらっていたので、
そこからのフィードバックが随分役に立ちました。
そこは大きなポイントだったと思います。 - 岩田
- でも、お客さんのコメントはすごくありがたい一方で、
迷ってしまう悩ましい部分もあると思うんですが、
そこはどうでしたか? - 中西
- そうですね・・・でも、先ほど堀から
“お化け屋敷”って言葉が出ましたけど、
お客さんに触ってもらう意味は、まさにそこだと思うんです。
というのも、今回開発中に“お化け屋敷プロデューサー”の
五味弘文(※14)さんという方の本を読んだんですが、
お化け屋敷でも、実際のお客さんの
反応をチェックしながら調整していくらしいんです。
それは『バイオハザード』をつくるときとまったく同じで、
プレイしてる人の反応を見ながら、
「ここの敵がでてくるタイミングをもう0.5秒遅らせよう」
とか、何度も調整していくんです。

五味弘文さん=日本のお化け屋敷プロデューサー。
- 岩田
- じゃあ実際に触ってもらっている反応を
生で見られるところに、
ものすごく価値があるんですね。 - 中西
- そうなんです。
ホラーをつくっていると麻痺していって、
怖さがわかんなくなるんですよ。
理屈としては“これで怖いはず”というように構成するんですが、
そこはあくまで理屈なので、
その結果を確かめるためのだいじな機会なんです。 - 岩田
- そこでお客さんがちゃんとおどろいてくれると、
安心できるし、手ごたえも感じますしね。 - 中西
- ええ。だから逆に
「え、そこそんなに怖い?」って思うこともあって、
社内でもけっこうテストをやるんですけど、
手に汗びっしょりかきながらやってるのを見て、
「お前、めっちゃビビリやなー!」って思います(笑)。
でも“怖さ”って、人間の感情の中でも
難しいと思うんですよね。
『バイオハザード』はどちらかといえば、
お化け屋敷のようなおどろかせ方なんですが、
同じものを見ても怖がる人と怖がらない人って、
けっこうわかれますし。 - 岩田
- たしかに怖さは
笑いより個人差が大きい気がします。
中には虚勢を張って怖くないフリをする人から、
ものすごく怖がる人まで、いろんなパターンがあるので、
とても悩むと思います。 - 中西
- はい。精神的なものですごく怖がる人もいれば、
直接おどろかすことでびっくりする人もいるし、
スプラッターなものを喜ぶ人もいるし・・・。
そういう意味では笑いに比べて、
ホラーはまだまだ研究の余地があるなぁと思います。 - 鈴木
- 音楽の演出でも、
あえて明るい曲を暗いシーンで流して、
ギャップで怖がらせることもしています。

- 岩田
- ふだん、バランスをとっているぶん、
突然ギャップがあると
人間の感情が不安定になりますからね。
今回、実際にできあがった手ごたえとして、
ホラーゲームが携帯型になるとどう変わりましたか? - 竹中
- “笑い”はみんなのものですけど、
“ホラー”は1対1のものだと僕は思うんです。
だから、ちっちゃい画面を覗き込む
携帯型の“没入感”が、ホラーとすごく相性がいいと思います。 - 鈴木
- 裸眼で3Dを見られることもすごくいいですよね。
気を紛らわせずに集中できます。 - 川田
- 探検しているような気分が強くなりますね。
たとえば「洞穴の中ってどうなってるのかな?」
みたいな奥へ奥へと潜っていく感じは3DSならではです。
そういう意味では、“船の中”という限定した舞台が、
非常にマッチしています。 - 中西
- 最初、E3後に「ホラーでいく」と決めた要因も、
携帯型で、かつ3Dという臨場感ですよね。
世界がそこにあって没入していく部分が、
「廊下の角の先に何かいそう」というところの、
「角の先」をリアルに感じさせられる。
“船”という閉塞感ある舞台にしたのも、
そこが活きると思ったからです。 - 川田
- でも船の中だけだと
どうしても変化に乏しくさびしくなるので、
雪山とか海岸とか、バリエーションもつくりました。 - 中西
- はい。“連続ドラマ”をイメージしていたのと、
携帯型は比較的、短いスパンの遊び方をするので、
舞台のバリエーションを増やすことで
コントラストをつくりたかったんです。
開放的なところから久々に船へ戻ってきたときに
「うわー、またここか・・・」
みたいな気持ちにさせたいなぁ、と。 - 岩田
- そのつくりもドラマっぽいですね。
- 中西
- はい。手ごたえとしてはうまくいったかなと思ってます。
- 川田
- ドラマ構成なので時間軸は一定じゃないんです。
じつはこれこそ、『バイオハザード』では初なんじゃないかな。

- 中西
- ああ、そうですね。
シナリオ側からも、プレイヤーに不安感を持たせるために、
海外ドラマ風のサスペンス要素を入れたかったんです。
「え、これどういうこと? どうなっちゃうの?」って
煙にまくような・・・。 - 鈴木
- あと、僕は“持ち運べる本格バイオ”っていうところも
すごく魅力的だと思っています。 - 中西
- え? でも、サウンド担当としては、
家でヘッドフォンで聴きながら
遊んでもらったほうがよりいいんでしょ? - 鈴木
- あ、そうか。両方楽しめるということで(笑)。
- 一同
- (笑)
- 堀
- 僕はちょっと違う切り口から言わせてもらいますと、
2画面なので、下画面をタッチするときに
一瞬、目を離すお客さんが多いと思うんです。
あの一瞬の間ができるのが、プレイしていると
わりとホラーとリンクしてくると思います。 - 岩田
- ああー、なるほど。
- 堀
- 一瞬目を離すことに
すごくためらいを感じると思います。
敵にやられちゃいますし、
目を離してる間に何か出てくるし。
そういう部分はホラーとして成立しているかなと思います。

- 岩田
- じつは怖さがより引き立つ構造なんですね。
もちろん、部屋で没入するのもひとつの遊び方ですが、
携帯型は遊ぶTPOの自由度を変える存在なので、
いままでと遊ばれ方が変わる気がします。
みなさん、そこについてはいかがですか? - 川田
- たとえばスリープしたら、いったん停止になりますよね。
ホラーとしてはあまり任意でゲームを止めたくないのですが、
携帯してゲームをするうえで必要だと判断しました。
クリフハンガー方式のようなシナリオ構成も、
自分がいまどういう経過をたどってきているかを
確認できるようなつくりになっていますので、
いままでの『バイオハザード』に比べて、
遊びやすくなっていると思いますよ。 - 中西
- なので、逆に本編はそれで割り切って、
でもやっぱり携帯型だから持ち寄って遊びたいよね、
ということで誕生したのが「RAID MODE」なんです。
