『ニンテンドー3DS』ソフトメーカークリエーター 篇
第24回:『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』
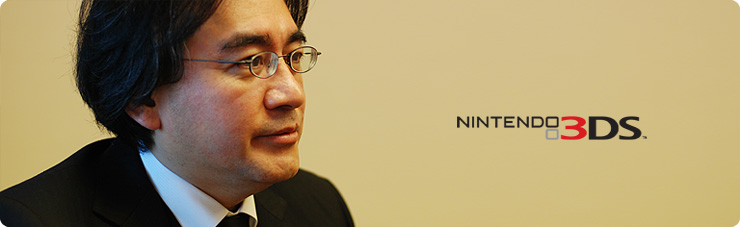
5. 小骨をくだいて、わざと残す
- 岩田
- 『ドラクエ』の冒険って、
自身を投影する度合いが高い理由のひとつに、
世界観にも『ドラクエ』らしさというものが
あると思うんですが、
眞島さんは、そこをどう思われていますか? - 眞島
- 『ドラクエ』で描かれるエピソードって、
全体としては壮大ではあるけれど
どこかの国の絵空事ではなくて、
一つひとつは本当に自分の
身の回りくらいの身近なスケール感で想像できる
シリアスな内容なんですね。
それが『ドラクエ』らしさじゃないかと思います。
僕が印象的なのは、
「嫉妬で犬に毒を盛る女」とか・・・。
もちろんリアルな描写はないですけれど、
遊ぶ人の心に強くイメージが浮かぶんです。 - 岩田
- それは、「ぜんぶ画面の上で描ききらなくても
お客さんには通じるんだ」っていうのを、
堀井さんは信じてらっしゃるからなんでしょうね。 - 眞島
- そうですね。
あとは全体的な設定でいうと、
『ドラクエ』って、魔界に行っても
タンスがあれば開けるし、同時に宝箱も開けるという
両極端なバランスが成立している世界なんですね。
それは魔界であろうがなんであろうが、
そういうスケール観でできることは維持しつつ、
善と悪の究極の戦いを描くということを
シリーズを通じてずっと維持しているんです。

- 岩田
- 当たり前のように感じていますが、
じつはけっこう、マネのできないことですよね。 - 眞島
- はい。そんな中でも
「あそこはどうなってるんだ?」と思うところに
すべて答えを用意しているのが、システムとしての
『ドラクエ』らしさなんじゃないかと思っています。
たとえばトビラがあれば絶対入れるし、
ツボがあったら割れるわけです。 - 岩田
- 「つくり手の都合によるウソはない」
ということですよね。 - 眞島
- 堀井さんがご自身で
どう思っているのかわからないですけれど、
そういうことでお客さんに
ウソをつかない暗黙のルールがあるんですね。 - 岩田
- わたしから見ると堀井さんは、
それを意識的にされている部分と、
自然とされている部分とが両立していて、
そのふたつが地続きになっている感じがしています。
堀井さんのゲームのつくりかたが
構造的に言語化できないのも、
それが地続きで存在しているからなんです。
だから、わたしはこうやって何度かお話を訊いて、
そのたびに「なるほど」とは思うんですけど、
結局、いまだに本当の全容は、わかっていないんです。 - 眞島
- 地続きという言いかたは、すごくふさわしいですよね。
「魔王の城が最初の町のすぐ近くにある」
という距離感の表現ひとつとっても、
都合が悪いからそこをごまかしたりとか
うやむやにしてる部分って、一切ないんです。 - 岩田
- 「主人公が勝手にしゃべらないこと」とか、
「誰でも遊べる基本的な作法」とかも、
ぜんぶ現実と地続きの話なんですよね。
・・・ああ、すみません。
わたしが勝手に盛り上がってしまいました。

- 一同
- (笑)
- 岩田
- 先ほど、今回リメイクするにあたって
「迷わない、不安にさせない、
わかりやすい『VII』をつくろう」という
コンセプトとお訊きしたんですが、
「ゲームがヌルくなったのか?」と
感じられてしまうこともありますよね。
そこの葛藤はどうやって埋めたんですか? - 堀井
- いや、石版は
たしかに見つけやすくなっていますが、
それ以外の部分では、
まだかなり歯ごたえはあると思いますよ。
あんまり簡単にしすぎると、
つまらなくなってしまいますし。 - 岩田
- いくら便利になっても、
導かれていることをやるだけになったら、
自分でやったという満足感がないですよね。
そのさじ加減は堀井さんの感覚で
調整されているんですか? - 藤本
- そうですね。たとえば、開発途中の段階では、
できるかぎりていねいに、やさしくつくろうと、
下画面に地図を表示するようにしたんですけど、
最初は宝箱のありかも見えていたんです。
でもそれは最終的に、
堀井さんの指示で表示をなくしました。
でもその一方で、石版は見せてるんですよ。 - 岩田
- 「答えをぜんぶ見せてはいけない」ということですよね。
たぶんそれをやるとお客さんは
「やらされている気持ちになるんじゃないか」という、
堀井さんのセンサーが動いたんですか? - 堀井
- うん、やっぱり見えている宝箱を取るというのは、
「作業になってしまう」と思うんです。
でも「行った先のほうに何かあるかもしれない」と思って
見つけるのは作業でなくなるんです。

- 岩田
- そこに表示があるかないかのちがいですけれど、
それが作業になるか、自分の冒険になるかは
大きく意味がちがってきますよね。 - 眞島
- そういう意味では、最初の島の構成は、
テストプレイをした堀井さんの意見で
開発の終盤にガーッと、変えたんですよね。 - 岩田
- まあ、いわゆる「ちゃぶ台返し」ですね。
- 堀井
- いや、アルテさんに自由にやってもらった部分も多いし
ちゃぶ台は、そんなにはひっくり返していないですよ(笑)。 - 一同
- (笑)
- 眞島
- でも、たしかにけっこう
大きな変更ではあったんですが、
そこを折れてしまうと、
『ドラクエ』がこれまで守ってきたものを
あきらめることになってしまうんですね。
だからそういった最後のさじ加減は重要で、
やり通すべきなんだと思っています。 - 岩田
- 「単純に難易度を下げた」わけではなくて
「いまの時代にいまのお客さんが
ストレスに感じるかもしれない部分を
徹底して、ていねいに調整しました」
というのが、正しい言いかたな気がしますね。
それはもちろん人によって多少個人差はあるけれど、
どの人から見ても理不尽と思わせないように、
「すごく普通の人」である堀井さんが、
小骨をひとつずつ、ていねいに、
抜いていくわけですよね。 - 眞島
- そうですね。でもたぶん堀井さんは、
その小骨を抜きはするけれど、同時にそれをくだいて
ほんのちょっとだけ残したりもするんです。
「コリコリしたところがおいしいでしょ?」って。 - 岩田
- ああ、なるほど。
わざと残して味わってもらうんですか(笑)。
「ここならちょっと苦労したほうがいいな」
という感じの、隠しのさじ加減があるんですね。 - 堀井
- ありますね(笑)。
ボクがいつもいちばん気にしているのは、
“とっかかりの部分”なんです。
そこでやるべきことがわかって
すーっと入ってきてもらえると、
そのあとは多少難しくても
お客さんはついてきてくれるんじゃないかと。 - 岩田
- 多少歯ごたえを残しておかないと、
平坦になりますからね。
だから今回も、最初の島の部分は
だいぶわかりやすく変えたけれど、
「本編のほうは歯ごたえは残していますよ」
ということなんですね。 - 杉村
- そこは、わたしが20年くらい前から
ずっとくり返し堀井先生から
お聞きしている言葉があるんです。
謎解きの難易度は、
「あそこは難しいから、
みんなは解けないんじゃないかなあ。
・・・ボクはクリアできたけどね」
というのを、“誰もが”感じるようなものを、
目指すべきだと。

- 岩田
- いや、『ドラクエ』のことをお訊きすると
毎回、堀井さんの話になってしまうんですよね(笑)。
でも堀井さんのものづくりの考えかたや
やってきたことの一つひとつが、
日本のゲーム業界をここまで引っ張ってくれた
大きな力のひとつなので、
いつも自然とそこに話が行きつくんです。 - 堀井
- ゲームをつくってるときって、
たいていの人は無意識に
いろんな行間を自分で埋めてしまうんです。
でも「ここまでやれば大丈夫だろう」と思っても、
人によって行間はちがいますから
「どう操作していいかわからない」とか
「何をすればいいのかわからない」みたいなことが
起きてくると思うんですね。 - 岩田
- はい。
- 堀井
- だから、操作性でいえばできるだけ
行間をつくらないようにしています。
たとえば、『ドラクエ』をはじめてつくったときのコマンド、
「はなす」とか「つよさ」とか
「どうぐ」とか、誤解しようのない言葉ですよね。
徹底的にわかりやすく、
しかも余分なことは言わないんです。 - 岩田
- けっして説明過剰じゃないんですよね。
そこが毎回すごくおもしろいところなんです。
たぶん「ていねいにしすぎる」ことは誰でもできるけど、
「説明すればいい」というわけではないんですよね。
「そんなことはわかってるよ」って
お客さんに思われたら、負けなわけですから。 - 眞島
- そういう意味では『ドラクエ』って、
いままで一度もチュートリアルモード(※18)はないんです。
チュートリアルモード=ゲームの導入部などで操作方法などを解説するシステム。
- 杉村
- そうですね、たしかに。
- 堀井
- わからないことがあると
不安に思うかもしれませんが、だからといって、
ぜんぶをわかってもらう必要はないわけです。
あまりに長いチュートリアルは見るほうも大変ですから、
もっと短時間で「わかったつもりになってもらう」ことが
重要なんですね。 - 岩田
- 堀井さんがおっしゃっている
便利さとかやさしさは、
一言では語れないんですよね。
でもきっと、最初に「わかった気になる」ことで
お客さんと信頼関係を結ぶことが
本当の目的なんでしょうね。
