「スーパーマリオ25周年」
ファミコンとマリオ 篇
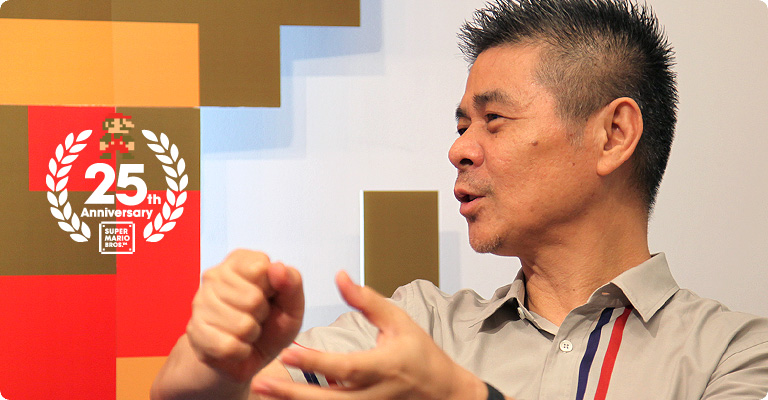
# 2. 家庭で『ドンキーコング』を
- 岩田
- リコーさんからの電話はどんな内容だったんですか?
- 上村
- 当時のリコーさんには
最新の設備を持つ半導体工場があったんですが、
稼働率が上がらずにお困りだったようなんです。
そこで「工場の使い道がないか1回見に来てほしい」と言われて。
その工場は当時、1割の稼働率しかなかったそうです。 - 岩田
- 大きな工場で1割の稼働率というのは悪夢ですね。
巨大な設備投資を必要とする半導体産業の採算を左右するのは、
工場の稼働率だと言われていますものね。
山内さんから「つくれ」という指令を受けてから
どのくらい経っていたんですか? - 上村
- 2カ月も経っていませんでした。
そこで、こちらとしてもいろいろ調べておこうと訪問してみたら、
むかし「テレビゲーム6」や「15」で
任天堂にテレビゲームの回路設計を教えてくれた方が
その工場にたまたまいらしたんです。
で、その人が「やろうやろう」と言ってくれまして、
でも、どのようなゲーム機をつくるのか、
めざすべきモデルがないと進めませんから、
そこで、ダメもとで言ってみたんです。
「『ドンキーコング』(※5)が動くものをつくれますか?」と。 - 岩田
- それはつまり、当時は大きなアーケード基板に
たくさんのICを載せることでようやく動いていた
業務用の『ドンキーコング』を、
「小さなワンチップにできますか?」とおっしゃったんですね。
『ドンキーコング』=1981年にアーケードで登場したアクションゲーム。ファミコン版は1983年7月に同時発売された。
- 上村
- そうです。そのとき、「こんな回路をつくることができるか」ではなく、
「この『ドンキーコング』ができるか」と言ったことが
いま思い出しても、大正解だったと思うんです。
というのも、リコーさんの技術者の人たちは
新しいテクノロジーへのチャレンジに飢えていたようなんですが、
それ以上にもっと大きかったことは、自分たちが頑張れば、
『ドンキーコング』を家に持って帰れるようになるぞと(笑)。

- 岩田
- 動機に火がついたわけですね(笑)。
- 上村
- ええ。彼らはゲーマーでしたから、
そのように考えてくれたのが幸運でした。 - 岩田
- でも、どうしてそう言ったんですか?
- 上村
- あの当時は、ハッキリ言って、
仕様書に書くことができないようなレベルだったんです。
そこで、『ドンキーコング』がどこまで再現できるのか、
まず現物をつくってみようと。 - 岩田
- たしかに実際にものをつくってみれば、
新しい機械にどんなことができて、
どんな表現ができるのかがすごくわかりやすくなります。 - 上村
- アーケードゲームをそのまま家庭用に移植することは
当時は不可能なことでしたが、
幸いなことにアーケードゲームの回路設計は
任天堂社内でやっていましたので・・・。 - 岩田
- 回路の中身を熟知していたんですね。
- 上村
- そうです。それと同時に、
宮本さんのようなソフト開発者がいましたので、
「最低でも、これは表現できるようにしてほしい」みたいに、
本来の魅力を残しつつ、みんなで相談しながら
ある程度単純化して、最大限の能力を引き出すことができたんです。 - 岩田
- 『ドンキーコング』という商品が社内にあったことの強み、
そして、それをつくったソフト開発者が社内にいたという強み、
さらに、ゲームセンター用の基板を、自分たちでつくっていた
ハード技術者も社内にいたという強みと、
合計3つの強みが当時の任天堂にはあったということですね。
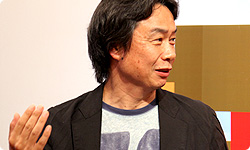
- 上村
- そう思います。
- 岩田
- もし、リコーさんから電話がかかってこなかったら・・・。
- 上村
- おそらくにっちもさっちもいかなくなって、
しまいには山内さんが業を煮やして
「アカン、やめよう」となっているか、
どっかのメーカーのICチップを買ってきて・・・。 - 岩田
- ふつうの商品をつくっていたかもしれなかったんですね。
- 上村
- ええ。ふつうにつくって、
すぐに消えてしまうような商品になっていたかもしれません。
でも、僕らとしてはそれは納得できなかったとは思います。
あの当時、僕らがいちばん気に入っていたソフトは
『ドンキーコング』でしたから、
どうしてもそれを載せたいという気持ちが強かったんです。 - 岩田
- 「3年間は競争相手が出ないような機械をつくれ」と
山内さんから言われていましたしね。 - 上村
- そうです(笑)。
- 岩田
- では、今度は今西さんにお訊きします。
任天堂がファミコンづくりに挑戦していく過程のなかで、
今西さんは開発の当事者ではないにせよ、
いろんなかたちで、開発がスムーズにいくように
側面からサポートされていたと思うんですけど、
上村さんたちのチャレンジはどんなふうに見えていましたか? - 今西
- 実はファミコンを立ち上げるとき、
僕はほとんどタッチしていないんです。
というのは、ゲーム&ウオッチのいろんな問題と・・・。

- 岩田
- ああ、そうか、そうでした。当時は
ゲーム&ウオッチのビジネスがどんどん大きくなってきて、
次々と起こるいろんな問題に今西さんは巻き込まれて、
それに対応することで手一杯だったんですよね。 - 今西
- そうです。なので、ファミコンで覚えていることは、
さっき話に出ていたリコーさんの工場の稼働率が低くて
「それは災難やなあ」と思ったのと、
CPUの“すごくいい石(※6)”が見つかったということくらいなんです。
その話を聞いて「ああ、それは良かった」と思ったことは
いまでも覚えています。
石=半導体のこと。元々はトランジスタ(半導体素子)が広く普及した当時、天然の石を使用していたことから、トランジスタのことを「石」と呼んでおり、そのトランジスタに代わるものとしてIC(集積回路)が登場した後もその呼び名が名残として残っていた。
- 岩田
- 上村さん、その“すごくいい石”を採用することになったのは
どんな経緯があったんですか? - 上村
- リコーさんから提案があったのは
6502(※7)というCPUだったんですが、
当時一般的には使われていなかったので、
それを理解できるのは、日本では東大と京大の
数人だけだという触れ込みだったんです。
だから、解析されにくいというのが採用の理由でした。 - 岩田
- 数人だけというのは大げさでしょうけど、
当時は本当に好きな人しか知らないCPUだったんですよね。
ちなみに、わたしの幸運も
ファミコンのCPUが6502だったことなんです。
たまたまわたしが大学時代にコモドール社のPETという
パソコンを趣味でさわっていたのですが、
そのパソコンのCPUも6502だったので、
社会に出た時点で最初から、
わたしは6502のエキスパートでしたから。
6502=アメリカのモステクノロジー社が1975年に発表した8ビットCPU。Apple IIで採用され一躍有名になったが、日本ではパソコン用CPUとしてはあまり普及しなかった。ファミコンで採用されたのは6502の互換CPU。
- 上村
- そうそう、岩田さんは当時、バグまで見せてくれましたよね(笑)。
- 岩田
- ああ、メモリを節約するテクニックのことですね。
「6502ではこんなこともできます。
設計上意図していたとは思えないので、バグみたいな使い方なんですけど」
とか言ってお見せしたことはありました(笑)。 - 上村
- で、本来なら『ドンキーコング』を移植したいわけですから、
業務用で使われているCPUを使うのが手っ取り早いんです。
ところがリコーさんは、自社でライセンスしていることもあって、
6502を売り込んできたんです。
ところが、社内で6502を採用したいと言うと、
「上村部長はゲームをつくっていないから、そんな判断をするんや」
とまで言われてしまったんです。 - 岩田
- 社内の技術者の抵抗にあうくらい、
社内の人たちも使ったことのないCPUだったんでしょうね。
当時は、8ビットのCPUとして最も普及していたのは
80系と呼ばれた8080やZ80などのCPUでしたし、
『ドンキーコング』をはじめとした業務用ゲーム機などでは
80系のCPUが使われることが多かったですからね。 - 上村
- でも、あとでそれがすごく幸いしたんです。
実際にファミコンが発売されてから、
他社の人が中を開けてもよくわからなかったわけですから。 - 岩田
- 他社さんがファミコン用のソフトをつくりたいと思っても、
CPUが何かわからないので、どうすることもできないわけですね。 - 上村
- ええ、任天堂はファミコンソフトを自社で全部まかなうつもりでしたから。
- 岩田
- 当時はライセンスビジネスが確立されていませんし、
ゲーム&ウオッチと同じように
自社製品だけでビジネスを展開するつもりだったんですね。 - 上村
- そうです。あと、マスコミ向けにファミコンを発表したときも
新聞などの反応がとても冷たかったんです。
どこにもキーボードが付いていなかったので・・・。

- 岩田
- 「これのどこがコンピュータなの?」ということですね。
- 今西
- ええ。われわれとしては、これはコンピュータなんだけど、
ソフトはわれわれがつくって供給するので、
お客さんが自分でつくらなくていいんですよと。 - 岩田
- 今では考えられないですけど、
当時のコンピュータというのは
お客さんが自分でプログラムを組むのが当たり前でしたからね。 - 今西
- そういうことです。
だから、ゲーム&ウオッチのようにワンハード=ワンソフトではなく、
ワンハード=マルチソフトでファミコンはやっていくんだと。
それにソフトは自社で全部やっていくのが最初の方針でした。 - 岩田
- 実際、ファミコンが発売されてから丸1年、
他社さんからファミコンソフトは出ませんでしたよね。 - 上村
- 『ファミリーベーシック』(※8)を共同で開発した
ハドソンさんのソフトが第1号でした。
ただ、その前に、ファミコンが発売されてから半年くらいで、
ナムコ(現バンダイナムコゲームス)さんの技術者のひとりが
ファミコンのCPUを見て、
「これ、6502じゃないか?」と言ったらしいんです。 - 岩田
- 当時、CPUが何かもわからなかったところから、
ファミコンの画面や音声の表示がどのような仕組みになっているかまで
ナムコさんは自力で解析されたそうですね。 - 上村
- それで最初につくられたのが『ギャラクシアン』(※9)で、
その後にすぐに『ゼビウス』(※10)も発売されることになったんです。
『ファミリーベーシック』=1984年6月に発売された、ファミコンの周辺機器のひとつ。BASIC言語を組み込んだカセットとキーボードの2点がセットになっており、かんたんなゲームプログラムを自作することができた。
『ギャラクシアン』=ナムコ(現バンダイナムコゲームス)が開発したシューティングゲーム。1979年11月にアーケードゲームで登場し、84年9月にファミコン版が発売された。
『ゼビウス』=ナムコ(現バンダイナムコゲームス)が開発したシューティングゲーム。1983年2月にアーケードゲームで登場し、84年11月にファミコン版が発売された。
