『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』
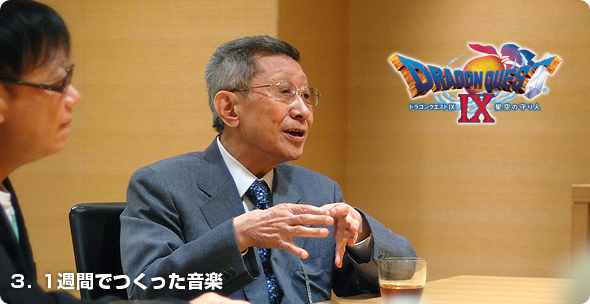
3. 1週間でつくった音楽
- 岩田
- そもそも、『ドラクエ』の曲づくりは
どうやってはじまるんですか?
どんなふうに先生にリクエストがあって、
先生はそれをどうやって受け止めて、
どのように曲をつくっていったんですか? - 堀井
- 最初は、すぎやま先生に対して
こういうゲームだから、町があって、
お城があって、フィールドも歩いてと
そんな感じで曲づくりをお願いしたんですよ。
当然僕たちは、ゲームっぽい曲が
上がってくるだろうと思っていたんですね。
そしたら、すごいクラシックが上がってきたので
それはもうビックリしちゃって。
ドット絵なのに音楽がすごすぎると思ったんです。
正直、「これ、合うのかなあ」と不安になったんですけど、
実際にゲームにのせて聴いてみると
ものすごくよかったんです。
それでもう、みんなで「いいねえ!」と(笑)。 - すぎやま
- いちばん最初の打ち合わせのときに、
「これはどういう世界のゲームなんですか?」と
中村光一さんに聞いたんですね。
そしたら彼の答えがひじょうに的確で。
「ひとことで言えば、中世ヨーロッパの騎士物語です」と。
それを聞いて、僕がパッとイメージしたのは
ワーグナーの「ニーベルングの指環」とかだったんです。
そこで、音楽のベースはクラシックでつくりましょうと。
その判断はよかったと思いますね。 - 堀井
- 本当によかったと思います。
- すぎやま
- だから長持ちしてるんですよ、音楽が。
- 岩田
- 当時流行っていた音楽を採用していたら、
こんなに長持ちしていなかったかもしれませんしね。 - 堀井
- 先生が当時言ったセリフで
すごく印象に残ってることがあって、
「なんやかんやある音楽で、
ゲームの音楽がいちばん長時間聴くだろう」と。
だから、聴き減りのしない曲をつくるんだと。

- 岩田
- そうなんですよね。
同じフレーズの繰り返しを
これだけ聴き続けることって、
他にはたぶんないと思いますし。 - 堀井
- ないんですよね。
- 岩田
- だから、すごく心に刺さるんでしょうね。
曲を聴いただけで、いろんなシーンを思い出しますし。 - すぎやま
- でもね、『ドラクエI』の曲は1週間でつくったんですよ。
- 岩田
- 1週間? それは衝撃(笑)。
- すぎやま
- 僕が呼ばれて行ったとき、
実は音楽はできていたんです。 - 岩田
- そうだったんですか。
- すぎやま
- ゲームもすでにマスターアップ直前だったんですよ。
それなのに千田さんが、
この音楽じゃダメだと全部キャンセルして、
そこに僕が連れて行かれたんですけど
「どれだけ時間をいただけるんですか?」と聞いたら、
「全曲を1週間でお願いします」と言われて。 - 岩田
- (笑)
- 堀井
- 開発期間は確か5ヵ月くらいだったんですよ。
- すぎやま
- まあ、1週間しかなかったんだけど、
モノをつくるというのは、誰でも
イメージがわく調子の波というのがあるんですよ。
調子のどん底に当たっていたら、
1週間ではできなかったですね、絶対に。
でも、『ドラクエI』の曲をつくったときは
調子の波のいいところに
たまたま当たったからよかったんでしょうね。 - 岩田
- なるほど。
筋のいいものに当たるのは、そういうときなんだと。 - すぎやま
- 僕はいつも言ってるんですけど、曲の楽想は、
5分以内でできたものが、だいたいいい曲なんです。
『ドラクエ』のテーマ曲のメロディも
5分で考えたんです。
調子のいいときだと、5分でパーンとできるんですね。
ところが、ああでもない、こうでもないと
こねこねして何日もかかるような曲だと、
だいたいダメなんですね。
でも最近は、『ドラクエ』を1本つくるのに、
3年有余の時間がかかるじゃないですか。
3年かかってる間には、波のいいときが必ずあるんですよ。
だから、調子の波のいい、波乗りのいいときの曲が、
『ドラクエ』にわりとそろうようになってるんですね。
おかげさまで。

- 岩田
- それにしても、先生がたまたま出したはがきが
たまたまプロデューサーの目にとまり、
1週間で音楽をと言われることからはじまって・・・。 - 堀井
- そもそも、このチームは
たまたま集まってできたチームなんですよ。
後から聞いた話なんですけど
鳥山さん(※15)が参加することになったのも、
担当のマシリト・・・鳥嶋さんが(※16)・・・。 - 岩田
- 「Dr.スランプ」に出てきた
ドクター・マシリトのモデルですね(笑)。
鳥山さん=漫画家の鳥山明氏。「Dr.スランプ」や「ドラゴンボール」などが代表作。『ドラゴンクエスト』シリーズ全作のキャラクターデザインなどを手がける。
鳥嶋さん=週刊少年ジャンプの元編集長の鳥嶋和彦氏。編集者として、「Dr.スランプ」「ドラゴンボール」などを担当。
- 堀井
- その鳥嶋さんが
「鳥山さんに刺激を与えようと思った」と言うんです。 - 岩田
- ゲームの仕事をすることで、
担当編集者として、本業のマンガに刺激を与えようという
意図があったんですか? - 堀井
- そうなんです。
それで「やったら?」みたいな感じで
気楽に言ったらしいんですね。
そこで、鳥山さんに絵を頼むことになったんですけど
最初に上がってきたのがドット絵だったんです。 - 岩田
- 鳥山さんがドット絵をですか!?(笑)
- 堀井
- だから、
「ドット絵じゃなくていいんです、先生」と(笑)。 - 一同
- (笑)
- 堀井
- そんな感じではじまったんですね。
でも、みんなある意味、すぎやま先生もそうですけど、
制限があるなかで、なんとか表現しようとしている。
逆にそこで工夫したことが、
いい方向にすごく出たと思うんですね。 - 岩田
- たまたま出会った人たちが、それぞれにある制約を
ネガティブではなく、ポジティブに捉えて
それでつくろうとしたのが、
『ドラクエ』だったんですね。 - 堀井
- そういう制約があったことが逆に
すごくいい結果につながったと思うんですね。

- 岩田
- ただ、ひとつつくり、ふたつつくり、
みっつつくりということで、つくればつくるほど、
雪だるまが転がるように、
『ドラクエ』は大きな存在になっていって・・・。
ゲームの新作が発売されるときに、
店頭に長蛇の列ができるというのは、
『ドラクエ』が最初だったと思ってるんですけど。 - 堀井
- 『ドラクエIII』のときがピークでしたね。
- 岩田
- 『III』が出たときは
社会現象のようになってしまって。
確か『III』の発売日は、
堀井さんは確かいろんなニュース番組に呼ばれて
テレビにも出演されてましたよね。 - 堀井
- テレビには、確か2〜3回出ましたね。
- 岩田
- テレビに映った堀井さんを見て、
わたしもゲームをつくる側にいましたから、
ゲームがあのように扱われることは
他人ごとながらとてもうれしかったんですね。
ちょっとしたご縁もありましたし(笑)。
ただ一方で、ゲームはどんどん大きくなっていき、
騒ぎもまたどんどん大きくなっていきましたよね。
そのようなゲームづくりをつづけていくときに、
堀井さんはどんなことを考えていたんですか? - 堀井
- 『III』まではそんなに悩まなかったんですよ。
もともとやりたかったことがけっこうあって、
それをそぎ落として、初代の『ドラクエ』をつくりましたし、
その後も、カセットの容量も増えてきましたし、
グラフィックの質も上がってきたということで、
『III』まではとんとん拍子でつくることができたんです。 - 岩田
- 確かにペースも早かったですしね。その頃までは。
- 堀井
- ところが、『ドラクエIV』(※17)で悩みましたね。
『III』までに、僕のやりたかったことは
だいたいやってしまったと。
その一方で、ユーザーのみなさんの期待は
どんどん大きくふくらんでいったんですよ。
だから、途方に暮れちゃいそうになりましたね、
「どうすんだよ、これ?」みたいに(笑)。 - 一同
- (笑)
『ドラクエIV』=シリーズ4作目の『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』。1990年2月、ファミコン用ソフトとして発売。DSなどでも、リメイク版が登場している。
- 岩田
- やっぱり悩むんですね、堀井さんでも(笑)。

- 堀井
- 悩みましたよ(笑)。
それにプレッシャーもすごく大きかったですしね。
だって、最初に『ドラクエ』を出したときは
自分の名前を呼ばれただけで
喜んでもらえましたけど(笑)。 - 岩田
- 「すぎやん」とお呼びしたくらいじゃ
もう喜んでいただけないと(笑)。 - 堀井
- 喜んでいただけないんですよね(笑)。
それに、時間とともに、
新しいゲームが次から次に出るようになって
そのゲームのなかではいろんなことが起きていて、
それが当たり前になっている人たちを相手に、
さらに「おっ!」と言ってもらわなきゃいけないわけです。 - 岩田
- よそのゲームではいろんなことが起きて、
いろんな新しいネタもできてますし、
いまさらこういうことでもいいのかなと
思うわけですね。 - 堀井
- ええ。新しいことをやりたいなとは思いつつ、
でも、あまりにも極端な方向に行っちゃうと、
わけのわかんないゲームになりかねないですし。
それに、何より王道のゲームとして
『ドラゴンクエスト』として
必ず押さえなきゃいけない部分もあるんです。
そのバランスをとるのが
けっこう難しかったりしたんですね。
