『PUNCH-OUT!!』
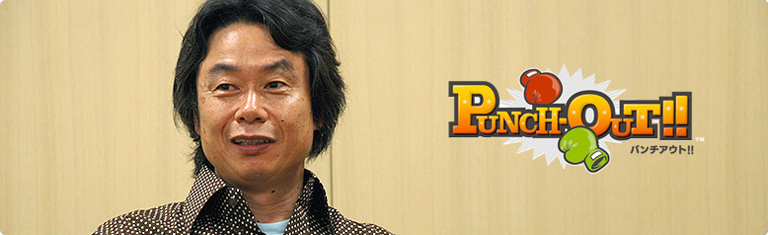
3. 巨大な方眼紙にドット画を描いて
- 竹田
- 『パンチアウト!!』をつくったとき
もうひとつの背景がありましてね。 - 岩田
- はい。
- 竹田
- それまではドット画で
1個ずつ絵を描くようなことをしていたんですけど、
デッサンでスッと描いてもらって
その絵をそのままゲームのなかに取り込むという
そういう基礎的な実験をいろいろはじめていました。
だからプロのアニメーターにも
描いてもらえるといったことも・・・。 - 宮本
- いや、なんか微妙に違うような・・・(笑)。
- 竹田
- 違う?(笑)
- 岩田
- まあ、25年も前の話ですからね(笑)。
- 宮本
- アニメーターの描いた絵を
そのまま取り込むツールは
当時はぜんぜん充実してませんでした。 - 岩田
- (笑)
- 宮本
- だから、机の大きさくらいの巨大な方眼紙を
わざわざ印刷してもらって、
全部手で描いてました。 - 竹田
- ただ、それを取り込める・・・。
- 宮本
- いえ、それをデータとして取り込むところが、
いわばプログラマーが楽だったというだけで、
デザイナーはぜんぜん楽ではなかったんです。 - 一同
- (笑)
- 宮本
- ものすごく大きなドット画を
全部手で描いていましたから。
そうやって描いたドット画を
スキャナーで入力するような仕組みが自動化されたと。 - 岩田
- じゃあ、絵は宮本さんが全部描いたんですか?
とても個性的な対戦相手が登場しますけど。

- 宮本
- それまでは自分で絵を描いてきたんですよ。
でも『パンチアウト!!』では
大きなボクサーを描くという時点でビビリましてね。
ちょっと自分の画力では描けへんと(笑)。 - 岩田
- 1.5倍の絵が表示できるということで
いつもよりも大きな絵を描く必要があったんですね。 - 宮本
- そこで、ボクサーの絵を試しに何人か描いて、
東京のアニメーターの香西(隆男)さんの会社、
スタジオ・ジュニオ(※10)に
持って行ったんです。 - 岩田
- 「新・巨人の星」とか「魔法使いサリー」の
アニメーションを描かれてた方ですね。
スタジオ・ジュニオ=アニメーターの香西隆男氏が東映動画退職後に設立したアニメーション制作会社。現社名はジュニオ ブレイン トラスト。
- 宮本
- ええ。僕にとってはそれが
アニメーターさんとの初めてのおつきあいになるんです。
そこで、喫茶店で絵を見せながら、
いろいろ説明したんですけど、
「面白い絵を描くねえ」とほめてもらったんですよ。
どう見たってヘタな絵なんですけどね。 - 岩田
- (笑)
- 宮本
- あの人たち、毎日上手な絵を見てるので、
ユニークな絵のほうが・・・。 - 岩田
- 魅力があると(笑)。
- 宮本
- だから、僕の描いた絵には
けっこうネタがつまってると思われたようなんですね。
そのとき「すごくいい絵、描くよねえ」と言ってもらえて、
それがもう僕にとっては励みになっていて・・・。
それで喜びながら京都に帰ってきて、
1週間くらいたつと
僕の元絵が立派なセル画になって戻ってきたんですよ。
きれいな色に塗られていて、
「あ、すごいボクサーらしくなった」みたいな(笑)。

- 竹田
- だから、さっき
プロのアニメーターに外注してもらったと。 - 宮本
- 合ってるのはそこだけなんですよ(笑)。
- 一同
- (笑)
- 宮本
- もう、その後が自動化されるどころか
ものすごく大変で(笑)。
まず、そのセル画を竹田さんに見せて
気に入ってもらえたので、
パーツごとの設計に入ったんです。
パンチやジャブなどの腕の動きから
顔を横向きにしたりとか、
いろいろパーツ分割して
それをセルにもう1回出したんですね。 - 岩田
- アニメーションとして動かせるように。
- 宮本
- それで上がってきたセルを拡大して
さっき言った巨大なトレーシングペーパーをのせて
1枚1枚、ドット画におこすようなことをしていたんです。
でも、とてもひとりでは描ききれないので、
僕がアウトラインをあたって、
アシスタントの女性に色を塗ってもらうようなことをして、
それを竹田さんのところに持っていくと。 - 岩田
- なんか、すごい力仕事のような気がしますね(笑)。
- 竹田
- ちょっと記憶があいまいなんですけど、
ツールができたのは『スーパーパンチアウト!!』(※11)のとき? - 宮本
- そうだったと思います。
『パンチアウト!!』のときにすごく大変だということがわかったので、
『スーパーパンチアウト!!』でだいぶ自動化されたんですね。
だから、1作目のときは大変でしたけど、面白かったですね。
僕はそこでアニメーターの方々とつきあいはじめることになって、
将来は小田部さん(※12)ともつながるし、
前田さん(※13)という「Dr.スランプ」を描いてた方にも出会って、
それで『ゼルダ』をつくるときのイラストを頼んだり、
『エキサイトバイク』をいっしょにつくったりしましたし。 - 岩田
- 大きなボクサーの絵が描けないと
宮本さんがビビッたことが、のちに
いろんなものにつながっていくということなんですね(笑)。

- 宮本
- そうなんです。
僕にとっての『パンチアウト!!』は
いろんな人とのつながりが生まれた
キッカケのソフトなんです。 - 岩田
- で、宮本さんがドット画以外に描いたのは?
- 宮本
- プレイヤーとレフリーです。
だから、スタジオ・ジュニオさんが描いた対戦相手より
質が落ちるんですけど(笑)。 - 竹田
- 観客席のなかに
マリオとドンキーコングもいて。 - 宮本
- そうでした。
マリオはいろんなソフトに出そうと思っていましたので
ちょうどいいと。
あと、会場でカメラのフラッシュが光るんですけど
そのような演出は、世界で初めて僕がやったんじゃないかと。
『スーパーパンチアウト!!』=『パンチアウト!!』の続編として、1985年に発売された業務用アクションゲーム。
小田部さん=アニメ「アルプスの少女ハイジ」などを制作した小田部羊一氏は、東映動画退職後に任天堂に入社し、マリオのキャラクターデザインなどの仕事にたずさわる。現在フリーとして活躍中。
前田さん=アニメーターの前田実氏。スタジオ・ジュニオに入社し、「Dr.スランプ アラレちゃん」「ドラゴンボール」「タッチ」などの大ヒットアニメの総作画監督を歴任した。
- 岩田
- そして続編の『スーパーパンチアウト!!』が出たのが・・・
- 宮本
- 翌年の1985年ですね。
業務用ゲーム機『スーパーパンチアウト!!』
- 竹田
- おかげさまで『パンチアウト!!』は
とても人気が出ましてね。
毎日、コインがたくさん入ってるという報告を受けてたんですよ。
それで、「続編をつくってくれ」と言われたんですけど
すごく困っちゃいましてね。
ボクシングでは、やることはやっちゃったわけですから。
そこで、反則ワザを入れるしかない、ということで、
足で蹴る人も出てきたりだとか
要は格闘技のような人が出てきたり、
もう何でもありの状態でつくったのが
『スーパーパンチアウト!!』だったんですね。 - 岩田
- ボクシングゲームの枠を超えて・・・。
- 宮本
- 後半はすごい動きをしてるんですよ。
ロープからロープに三角跳びをしたりとか(笑)。 - 岩田
- プロレスじゃないんだから(笑)。
- 宮本
- そこはもう独壇場でしたね。
奔放な竹田さんの。 - 竹田
- 武器を持たせようかとか
とてもまじめに議論もしたんですよ。
でも、そこまでするのは
あまりにも変だよねということなって(笑)。 - 一同
- (笑)
- 岩田
- 宮本さんはそのとき、
どのように関わったんですか? - 宮本
- 僕は、絵だけでサポートしてました。
だから、仕上げにもあまり入ってないんですね。 - 岩田
- それにしても、
かつて『パンチアウト!!』について語り合ってたという、
竹田さんと宮本さんの姿は、どうしても想像できないです(笑)。
でも、それがルーツなんですよね。 - 竹田
- ただ、この『スーパーパンチアウト!!』が最後でしたね。
いっしょに仕事をする・・・。 - 宮本
- そうですね。NINTENDO64の時代になるまで・・・。
- 竹田
- その頃はわたしはもうハード部門ですから。

- 岩田
- いっしょにソフト開発をしたのは
『スーパーパンチアウト!!』が最後だったんですね。
宮本さんに訊きたいんですけど
竹田さんのゲームづくりの特徴は
どういうところにあったんですか? - 宮本
- ひとことで言うと、やっぱり奔放ですね。
- 岩田
- ピザ・パスタの命名とか?(笑)
- 宮本
- 発想がとても自由なんですね。
だから、見習うべきところがいっぱいあって・・・。
たとえば、新しくて困難な命題を与えられたとき
「どうしろと言うの?」と思う人が多いんですけど、
竹田さんは「なんとか自分たちでやろうよ」
と考える人なんですね。
ビデオゲームというもの自体が
どうつくっていいかわからない時代に、
ビデオゲームがつくれる会社に頼みに行った人たちと、
自分たちだけでつくろうとしていた人たちの、
2つの流れが任天堂のなかにはあって、
竹田さんは後者の旗手として
いまも時代を動かしていると思うんです。
ただ、ちょっと早すぎるところもあって・・・。 - 岩田
- 早すぎる?
- 宮本
- いまでこそ
Wiiでモーションセンサーは当たり前になりましたけど
グローブのインターフェイスはちょっと早すぎたかなと。 - 岩田
- なるほど(笑)。
- 宮本
- だから、竹田さんという人は
10年後にいいということを考えられる人なので、
それが果たして、いまの時代に合っているのか、
それを「いま風」に翻訳する役目として、
僕がここにいるんだと思っています。
