『キキトリック』

- 岩田
- 今回はWiiソフト『キキトリック』について
お話をお訊きしようと思います。
みなさん、よろしくお願いします。
- 一同
- よろしくお願いします。
- 岩田
- 最初にオトデザイナーズ(※1)さんから
お話をいただいたのは、何年前になりますかね?
株式会社オトデザイナーズ=埼玉県和光市に本社を置く“音”と“耳”をキーワードに新たな価値を創造する企業。坂本真一氏が代表を務める。
- (オトデザイナーズ)坂本
- もう4年半前ですね。
- 岩田
- 随分と時間がかかってしまいましたけれども。
- (オトデザイナーズ)坂本
- 長かったです(笑)。
- 岩田
- 今回、「非常に面白い音の技術がある」ということで、
“聞き取ること”や“聞き分けること”をテーマとした
いままでにあまり前例のないジャンルのソフトができました。
まず、それぞれ自己紹介をお願いしたいのですが、
オトデザイナーズさんとはどんな会社なのか、
というところからご説明をお願いできますか?
- (オトデザイナーズ)坂本
- はい。オトデザイナーズの坂本真一です。
もともと、わたしはリオン(※2)という
補聴器のメーカーで聴覚の研究をしていました。
専門は難聴と補聴で、一般の方の聴覚心理なども研究していました。
じつは、聴覚心理には100年近く研究されている
長い歴史があって、非常に興味深い現象が
山のようにあるんですけど、
どれもほとんど世の中に出ていないんです。
ノイズ君の音声の技術は、
同志社大学の力丸先生(※3)からご紹介いただいて
研究していたんですが、周りのメンバーに音を聞かせて
何と言っていたかを答えてもらうと、
聞き間違えの珍回答が山ほど出てきて
大変興味深かったんです。
力丸先生=力丸裕。同志社大学 生命医科学部 医情報学科教授。
- 岩田
- 「これほど面白いんだから
エンターテインメントの世界とつながるはずだ」
という思いが最初のうちからあったんですか?
- (オトデザイナーズ)坂本
- はい。それで「これをゲームにしたら・・・」と思って、
任天堂さんにご紹介した、というのが経緯になります。
- 佐藤
- 任天堂、企画開発部の佐藤です。
『キキトリック』のディレクターとして
企画から開発まで全般にかかわりました。
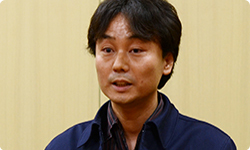
- 岩田
- 佐藤さんは『キキトリック』にかかわって
どれくらい経ちましたか?
- 佐藤
- 『DSテレビ』(※4)を担当した後から
ずっとつくっていましたので、丸3年になります。
『DSテレビ』=『ワンセグ受信アダプタ DSテレビ』。2007年11月に発売されたニンテンドーDS用ワンセグ受信チューナー。ニンテンドー3DSでも使用可能。
- 岩田
- では、任天堂の坂本さん。
- (任天堂)坂本
- はい(笑)。どうも。
企画開発部の坂本(賀勇)です。
『キキトリック』のスーパーバイザー(監修)として、
「このテーマをどうやってゲームデザインに落とし込むか」
「わかりやすく遊んでもらうためにどうすればいいか」
そういったことを少し離れたところから、
いろいろ意見を述べる役割をしていました。
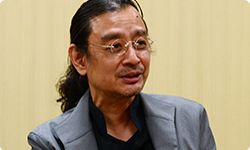
- 岩田
- ではまず、
『キキトリック』の紹介デモにもあるとおり、
ノイズ君のこうした劣化雑音(※5)の技術を紹介されたとき、
佐藤さんの第一印象はどうでしたか?
劣化雑音=劣化雑音音声。音声信号の振幅包絡(しんぷくほうらく)を保ったまま、いくつかの帯域雑音に置換した合成音声のこと。
- 佐藤
- 僕がいちばん最初に紹介されたときは、
ある短い一文を聞いたんですが、
「ザザザザザ・・・」という雑音にしか聞こえなくて、
声としてはまったく聞き取れませんでした。
でもそのとき、スタッフのひとりが、
「“血みどろのなんとか・・・”って聞こえる」って言ったんですね。
そんなはずはないと思ったんですが、
次に聞いてみると、僕にもそう聞こえたんです。
でも、じつはそれは答えじゃなくて正解は
「ショートケーキを買ってきた」だったんです。
それでもその場にいた僕たち全員、
「ショートケーキを・・・」が、
「血みどろの・・・」としか聞こえなくなってしまって(笑)。
- 岩田
- 1回、そう思い込んでしまうと
「血みどろの・・・」にしか聞こえないんですよね。
- 佐藤
- そうなんです。その瞬間、
「これはすごく面白い」と感じました。
- 岩田
- 人によって、聞こえ方が違うところが盛り上がりますよね。
いったん誰かが「こうだ!」って言うと、
みんながそれに激しく引っ張られて
正解からますます遠ざかってしまう、
何とも言えない独特の面白さがあります。
佐藤さんはこのソフトを預かったとき、
わりとすぐにWiiでつくるものだと思ったんですか?
- 佐藤
- いえ、当初は携帯機で
パーソナルな音の楽しみ方を追求していたんです。
でも「血みどろの」から正解に至るまでの周囲の笑いと、
開発していく途中でまわりの人が
「こう言ったんじゃない?」って反応してくるのを見て
「これはゲームのまわりにいる人たちを呼び寄せる力がある!」
と思いはじめて、
Wiiでの開発を視野にいれてつくりはじめました。
でも今回、いちばんはじめの開発ノートを見たら
“台所にいるお母さんを振り向かせる”
と書いてあって、びっくりしました。
たしか、オトデザイナーズの坂本さんとの打ち合わせで
「プレイしているときに離れている家族を振り向かせたいね」
という話が出て、それを岩田さんにお伝えしたら
「だったら家庭の中心にいるお母さんを振り向かせてください」
と言われたんです。
- (オトデザイナーズ)坂本
- リビングでWiiをやっている子どもたちがいて、
台所でお母さんが背を向けて料理をつくっているときに
音が聞こえてきて、バッと振り向いて参加しちゃう・・・
そんなイメージですね。
- 佐藤
- そう考えると、だいぶ初期のころから
“振り向かせること”を意識してつくっていました。
だから、必ずしも全員がWiiリモコンを持つ必要はなくて、
まわりの3人は好き勝手に言い合える形を目指しました。
- 岩田
- まさに“参加人数自由”ということですね。
一方、『リズム天国』(※6)のようなゲームはあっても、
いままで音を聞くことそのものをテーマにしたものは、
ほぼ前例がありませんでした。いわば、
ゲームの文法からつくらないといけないわけですから、
基本構造をつくるのに苦労したんじゃないですか?

- ※6『リズム天国』=2006年8月、ゲームボーイアドバンス用ソフトとして発売されたノリ感ゲーム。シリーズ最新作は、2011年7月に発売されたWii用ソフト『みんなのリズム天国』。
- 佐藤
- はい。最初の半年間はコンピューターで組まず、
拾ってきた音を逆再生したり、早回ししたり、
同志社大学の力丸先生のところに行って、
音の面白い例を聞いたりしていました。
- 岩田
- 研究者の先生にヒアリングに行っていたんですね。
- 佐藤
- はい。だから実際にゲームをつくりはじめたのは
だいぶ時間が経ってからです。
リズム感や音階ではなく、
“不思議な音”というテーマだけで
ゲームがつくれないか、半年間模索しつづけました。
それでオトデザイナーズさんに協力していただいて、
ある程度、先が見える形まで持っていけたんです。
- (オトデザイナーズ)坂本
- 佐藤さんからはひんぱんに、
「もっとネタがないですか?」ってメールが来ました。
いくつかつくって送ってしばらくすると、
「すごく面白かった!」って返信があるんですが、
最後に「でも使えませんね。ほかにないですか?」
と書いてあるんです(笑)。
- 佐藤
- やはり学術的なアプローチよりも
みんなでワッと笑い合えるものを目指したかったので、
たとえばオノマトペ(擬音語)でゲームをつくれないかとか、
視覚でいうゲシュタルト崩壊(※7)を音で応用できないかとか・・・
いろいろしつこく試していったら、意外とネタが集まりました。
ゲシュタルト崩壊=ひとつの文字を見つづけていると、意味のない線の集合体に感じられるように、全体性を見失って個別のみを認識するようになる現象のこと。
- 岩田
- 膨大にある研究成果の中から、
時間とエネルギーをかけて、
娯楽に応用できるネタを選んでいったんですね。
- 佐藤
- はい。それで最終的に上司の坂本さんから
「“耳の職人(ミミプロ)”という形でまとめたらどうか」
「もっと音を身近に感じさせたらどうか」
とアドバイスをもらったんです。
そこで、“不思議な音を聞き取る”という方向性と、
騒がしい駅の「売店」みたいに
さまざまなシチュエーションで“音を聞き分ける”
といった遊びの方向性にまとめていきました。
- 岩田
- 「売店」というのは、うるさいところで
いろんな注文が同時にやってくるのを
聖徳太子のように聞き分ける遊びですよね。
- 佐藤
- はい、これはカクテルパーティー効果(※8)を使ったものです。
カクテルパーティー効果=さまざまな雑音が存在する状況の中、必要な情報を選別できること。
- (オトデザイナーズ)坂本
- “カクテルパーティー効果”というのは、
立食でカクテルを飲みながら大勢が談笑する
カクテルパーティーってありますよね。
あれを音響物理的に分析すると、
うるさすぎてまともに会話ができないはずなんです。
でも、それが人間にはできてしまう。
その人間の聴覚の非常にすぐれた能力のことを
そう呼んでいます。
- 岩田
- 音声信号として分析すると、
その人の声だけを抜き出すのは非常に困難なはずなのに、
なぜか人間はうるさいところでも会話ができてしまうんですね。
- 佐藤
- 聞き取りのゲームとして身近なネタを使うことで
「ああー、こういう人いそうだな!」っていう
「あるある感」も出せたと思います。
そういうふうにふくらませていったら、
「ミミプロ」という8種類のまったく異なる
耳の力を試すゲームが完成したんです。
